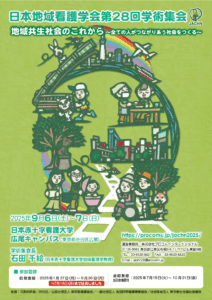日本地域看護学会第28回学術集会で介護のセミナーをします/日本赤十字大学9月6日(土)

この度、プライマリー・アシスト株式会社様よりご依頼をいただき、日本地域看護学会第28回学術集会にてセミナー講師として登壇することとなりました。ランチをいただきながらセミナーを受講できるランチョンセミナーを担当します。
学会の参加は看護師・保健師・助産師に限られます。また、セミナーは席数に限りがあるため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
セミナーテーマ
介護と仕事の両立支援
~介護する人される人の深層心理~
抄録
高齢者の増加に伴い、在宅介護を行う家族が増えています。その多くは働きながら介護をしていますが、看護においては地域看護と産業保健がまだ分離しています。介護者は自宅にいようと職場にいようと、その人自身であることに変わりなく、地域共生社会をつくるために訪問看護師と産業看護師がつながる必要性があると考えます。
【目的】
介護家族が自宅にいようと職場にいようと、共通しているのは『心理状態』です。介護で生じるストレスや暴言・暴力、介護離職、介護自殺などの諸問題は、介護に関わる両者の心理状態が影響しており、深層心理の働きを看護師が知ることは問題解決の糸口になると思われます。介護家族に関わる専門職として、看護コミュニケーションの向上を図りましょう。
【内容】
現代社会は変化のスピードが速く、とくに人間関係においてはジェネレーションギャップが問題となりやすい状態にあります。『団塊の世代が生きた時代の価値観』と『若者の価値観』を比較することで認識を変え、看護における関わり方を考察します。また、介護とはそもそも何か?私たちは何のために長生きをし、家族と共に自宅で過ごしたいのか、原点に立ち返ることで介護の意味を再認識します。
【考察】
要介護者にもっとも影響を与えるのは、常にそばで関わっている家族の心理状態です。ということは、家族に関わる看護師は『要介護者(第1)・介護家族(第2)・看護師(第3)』という客観的ポジションをとります。看護師が行う『言葉かけ』が家族の心理状態にどのような影響を与えるかを考察した上で、結果的に要介護者にどのような状態をもたらすかを併せて考察し、より良い関り方を工夫する必要があると考えます。
【結論】
地域包括ケアシステムにおいて、介護は『共助』から『互助』へと比重が変わりつつあり、地域及び職場で関わる誰もがケアラーになる必要性があるでしょう。地域看護・産業看護においても、介護家族の心の支えになることは必須であり、当事者を含めた家族へと看護の視点を広げていきたいと思っています。
企業の皆さまへ
『介護・がんで悩む社員への関わり方』
「煩雑な介護保険」と「社内の規約」の狭間で思い病むご家族の負担がわずかでも軽減するよう、今回の学会で「産業保健師」と「訪問看護師」の共通認識を図り、介護離職の防止に努めてまいりたい所存です。社内セミナーご要望の際は、ご一報いただければ有難く存じます。
看護師・保健師の皆さまへ
介護は日常生活の支援でしょうか?ならば介護職と違いがありません。ランチョンセミナーで看護の考え方・介護の考え方を共有できましたら幸いです。また、2022年には第26回日本看護管理職学会学術集会に「看護のアドベンチャービジネス」で登壇し、その後「看護展望」に執筆した経緯もありますので懇親会等で情報共有できますと幸いです。
学会は日本赤十字看護大学で開催されますが、ハイブリッド形式のためオンラインで視聴することも可能です。お会いできることを心より願っています。
日本地域看護学会第28回学術集会の詳細
 新着記事
新着記事
お知らせ一覧
-
看護師と話そう!介護の悩み・病気との付き合い方/イオンのケア活
-
『MySCUE』で動画を配信しています
-
イオンで介護のお困りごとを相談できる
-
看取り対話師研修 募集要項
-
【動画でわかりやすく解説】介護保険利用までの流れ3ステップ
-
「心の介護相談室」をイオンモール茨木に出展しました
-
どこに相談すればいいかわからない介護のストレスは…「心の介護相談室」へ
-
【人事・労務担当者様】介護・がんで悩む社員への関わり方セミナーを行いました
-
社内を支える「介護両立準備セミナー」を行います
-
介護・看取り・がんにまつわる社員への寄り添い方セミナーを行いました
-
「心から看る介護と認知症」のお話会をしました
-
「離職を防ぐ親のみとり介護サポート」ご案内